#はたらく
カーボンレスな社会の実現へ
熔鉱炉の炎に未来を託す
日本冶金工業株式会社大江山製造所製造部製錬課 矢野祐仁さん
2025.11.07
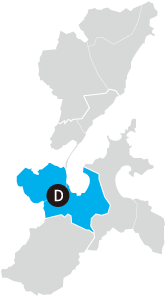


1942年以来、宮津の地でステンレス鋼の主原料であるフェロニッケルの生産に取り組む日本冶金工業株式会社大江山製造所。工場の煙突から立ち上る白い蒸気、敷地の近隣を彩る桜や銀杏は、地元の人であれば誰もが知っている光景です。ただ、その内部でどんなものづくりが行われているか、知っている人は少ないのではないでしょうか。
今回お話を伺ったのは製造部製錬課の矢野祐仁さん。約20年に亘って熔鉱炉の操業を担っていきたベテランの技術者です。矢野さんによると、ステンレスの原料となるフェロニッケルルッペ(フェロニッケルの粒鉄)を製錬する「熔鉱」という作業は“面白い仕事”だそう。その言葉を深掘りすると、勤務に対する責任感と強い探究心が見えてきました。
日本を代表するステンレスのリーディングカンパニー
――まず、日本冶金工業株式会社(以下、日本冶金)全体の事業内容について教えてください。
「冶金(やきん)」とは鉱石から金属を取り出し、加工することを言います。当社では、ここ大江山製造所でステンレスの原料となるフェロニッケルルッペを生産し、それを神奈川県にある川崎製造所へ運びステンレス鋼に仕上げています。
ステンレスは、錆びにくく、強度や耐熱性が高いという利点に加え、リサイクル性にも優れています。近年はサステナブル素材として注目を集め、キッチンのシンクやエレベーター、エスカレーター、さらに病院の手術器具やスマートフォンの部品など、さまざまなシーンで活躍しています。

――企業としての強みは何ですか?
日本冶金は、鉱石から金属を取り出す「製錬」からステンレスの「製造」まで一貫して行う日本で唯一のステンレスメーカーです。多くのメーカーが外部から原料を調達する中、当社は自社でフェロニッケルルッペを生産できるため、安定した供給を実現しています。
またステンレス鋼だけでなく、耐食性、機械的性質、物理的性質を高めたニッケル合金を製造し、多種の製品群によって多様なニーズに応えています。
――では次に、大江山製造所内で行っている作業について教えてください。
大江山製造所の製錬工程は「原料工程」「熔鉱工程」「選別工程」の3段階に分かれています。
まず「原料工程」では、原料となるニッケル鉱石を2週間かけてニューカレドニアから取り寄せます。宮津の人なら、宮津湾に浮かぶ大きなタンカーや、天橋立と文殊堂を結ぶ「回旋橋」が回転して船が通る様子を見たことがあると思いますが、実はあの船こそ、大江山製造所に原料を届けているのです。

その後、工場に搬入された鉱石を3mm以下に粉砕し、リサイクル原料や無煙炭、石灰石と混ぜて「ブリケット」と呼ばれる塊にします。
次の「熔鉱工程」で、このブリケットを直径4m、長さ72mの巨大な熔鉱炉「ロータリーキルン」に投入し、最高1300度の高温で10時間かけてゆっくり熔かします。熔鉱炉が回転し内部の原料を移動させることで、炉の中で均一に燃焼と還元が起こり、「クリンカー」と呼ばれる物質が焼き上がります。
それを最後の「選別工程」で再度粉砕し、その中からステンレスの原料となるフェロニッケルルッペを回収するのです。

世界唯一の技術を扱うスペシャリスト
――矢野さんはどの工程を担当されているんですか?
私は入社以来20年間、熔鉱工程を担当しています。先ほどもお話した通り、大江山製造所では、ロータリーキルンという熔鉱炉だけを使う「クルップレン法」をとっています。これは、電気炉を使う一般的な製錬と違い、少ない電力でも効率的にフェロニッケルルッペを生産することができます。この技術での生産は珍しく、取り入れているのは世界でも大江山製造所だけなんです。

――「世界中で大江山製造所だけ」とは驚きました。
そうでしょうね。私も宮津で生まれ育ちましたが、入社するまで全然知りませんでしたから。でも、実際に働いてみると熔鉱炉って面白いんですよ。操業の仕方によってフェロニッケルルッペが大きくも小さくもなるので、いかに大きく成長させるか、毎回工夫のしがいがあるんです。

――熔鉱炉の操業は機械で自動的にするものだと思っていました。実際は、矢野さんら製錬課員が状況に合わせて繊細な作業をしているんですね。
機械が大部分を担っているのは事実ですが、観察と判断は人にしかできません。熔鉱炉の炎の色や排気の具合などを注意深く観察し、最適な状態に導きます。フェロニッケルルッペを少しでも大きく成長させることができれば、最終的なフェロニッケルルッペの回収率が高まり生産効率も上がります。責任のかかる作業ではありますが、それ以上にやりがいがあります。

――臨機応変な判断が求められる、専門性の高い仕事ですね。もともと、そういう分野を勉強されていたんですか?
いえ、基本的なことは入社後3か月間ある集合研修で学びました。その後も、先輩がマンツーマンで教えてくれるので、仕事をしながら自然と身についた感じです。
――では、現場で経験を重ねながら徐々に知識やスキルを高めていったんですね。
自分で考えながら学ぶこともありますし、周囲と相談して解決することもあります。業務は基本的に1班4名の班単位で行うので、気になる点は同じ班のメンバーと情報交換します。班長になった現在は、後進の育成のために知識や情報を共有し、全体のレベルを底上げするよう心がけています。

今日も現場に響く「ご安全に」の掛け声
――直径4m、長さ72mもの巨大な熔鉱炉を扱うには安全面の配慮も必要だと思います。どんな取り組みをされていますか?
工場内では、日頃からこまめに設備点検する他、社員同士が互いに「ご安全に」と声を掛け、注意喚起と相互確認を行っています。
また社員の体力面での安全を考慮し、勤務は4班3交替制です。朝7時~15時、15時~22時、22時~翌7時、休日というサイクルを1週間ごとに交替し、無理のないシフトが組まれています。勤務時間中も、熱中症対策として毎日ペットボトルの水が1本支給され、自動販売機で飲みたい時に購入することができます。
やはり1300℃に燃え盛る熔鉱炉の影響力は大きく、そばに立つと肌で熱波を感じるほど。工場内の気温も40℃近くに達するため、このような取り組みが行われているのです。

――機械設備の安全だけでなく、それを扱う社員さんの体力面にもしっかり配慮されているんですね。
はい、ですが決して体力的にきつい仕事ではありません。私も最初は、製造所勤務=肉体労働をイメージしていましたが、実際は機械の操作が中心です。それに工場内には、仕事の疲れや汚れを流すための大浴場や、地元の食材を使った手料理をワンコインで食べられる食堂も完備されています。仕事に集中できる環境が整っているので、長く続けやすい職場です。

美しい環境を美しいまま次の世代へ
――大江山製造所は「よさの大江山登山マラソン」や「みやづ産業フェスタ」の参加など、地元の取り組みに積極的に参加されていますね。
はい、他にも2ヵ月に1度は製造所周辺の国道を社員で清掃し、年2回行われる「クリーンはしだて1人1坪大作戦」という清掃活動には家族で参加しています。
こうした地域の活動に参加すると、改めて「宮津は、天橋立を大切にしている街だな」と実感します。
――たしかに、天橋立の美しさは地元の人たちの努力の賜物だと思います
大江山製造所でも、隣接する天橋立の美しい風景を守るため、工場から出る排水や排ガス管理には細心の注意を払っています。例えば、工場用水として使用した水は排水処理装置で濾過し、きれいな状態に戻してから海へ流します。また、排ガスも電気集塵機など複数の工程を経て浄化しています。ですから、当製造所の煙突から出ているのは、煙ではなく浄化を経た水蒸気なんです。

――普段、私たちが見ている白い煙は水蒸気ということですか?
はい、そうです。煙は、ばい塵(物が燃えた際に発生する産業廃棄物)が混じると黒く染まってしまいます。その点、大江山製造所では徹底した管理によって水蒸気を出しているため、常に白色をしているのです。
――他にも環境のために取り組んでいることはあります?
先ほどお話しした「クルップレン法」は、効率が良いだけでなく、省電力で環境にも優しい製法だと考えています。当社では、クルップレン法の特性を活かしたさまざまな工夫によって二酸化炭素の排出を削減し、「カーボンレス(脱炭素)」に向けた取り組みを行なっています。
具体的には「カーボンレス・ニッケル製錬への挑戦」を掲げ、製造所内で4つの施策を進めています。まず1つめはリサイクル原料の多様化と使用拡大です。ニッケル水素電池などのリサイクル原料に含まれるニッケルを回収し、従来のニッケル鉱石に依存しない「都市鉱山」へのシフトを目指しています。
――聞き慣れない言葉ですが、「都市鉱山」とはどういう意味ですか?
身の回りにある家電やパソコン製品に使用されている金属資源を、都市に存在する「鉱山」に見立てて表現したものです。天然資源や自然環境の保全が重要課題である現在、既に製品化されているものの中から再度ニッケルとして資源化します。大江山製造所でも、現在使用しているニッケル原料の半分以上がリサイクル資源に切り替わっています。
2つめは燃焼エネルギーの転換です。これまで熔鉱炉の加熱には石炭を使ってきましたが、2025年8月からは二酸化炭素の排出の少ないLNG(液化天然ガス)へ転換しています。同じく3つめも石炭に変わる素材の転換で、熔鉱工程で還元に用いる石炭を使用済みプラスチックへシフトしつつあります。
そして最後は、フェロニッケルルッペの製造過程で生まれる副産物の低減です。例えば当社で扱う「ナスサンド」という製品は、フェロニッケルルッペの製錬の際に生まれる副産物を有効に活用したもので、コンクリートの原材料である骨材の一つとして使われています。
これらの取り組みが功を奏し、2013年からの10年間で二酸化炭素の排出量を50%まで抑えることができました。

――今後も継続する予定ですか?
はい、2030年までに二酸化炭素の排出量を70%削減する計画です。
サステナブルな社会の実現に向け変革が進む中、ステンレス業界においては、リーディングカンパニーである日本冶金が抱える責任は大きいと思います。
フェロニッケルルッペの生産を請け負う大江山製造所としても、その役割を果たすべく取り組みを加速させています。操業を一手に担う我々製錬課も、原料や燃焼エネルギーが変わった分、操業方法を大きく変え、新たな技術を模索している真っ最中です。これまで代々受け継いできたものが全く通用しない場面もあり悩むことも多いですが、技術を一から確立していくのは面白くやりがいがあります。試行錯誤を繰り返し、確かなものを次の世代に伝えていきたいです。
